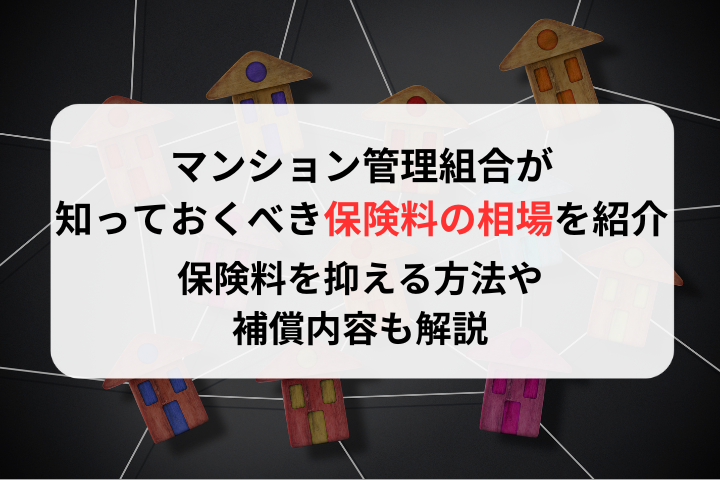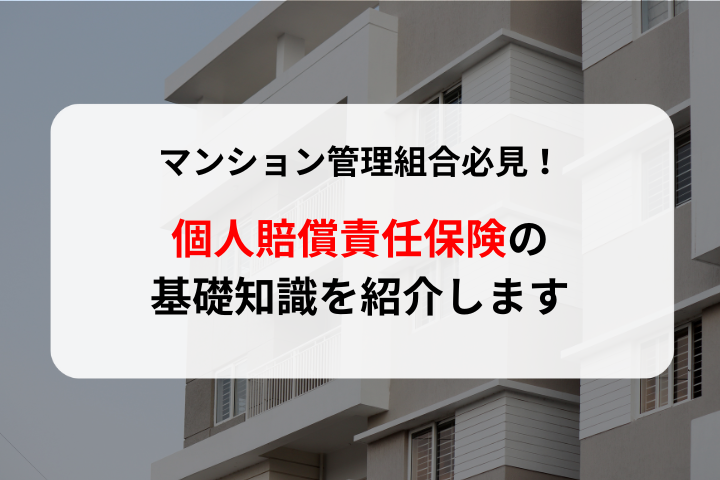マンション総合保険に付帯される地震保険は加入するべき?保険の対象やメリットを解説
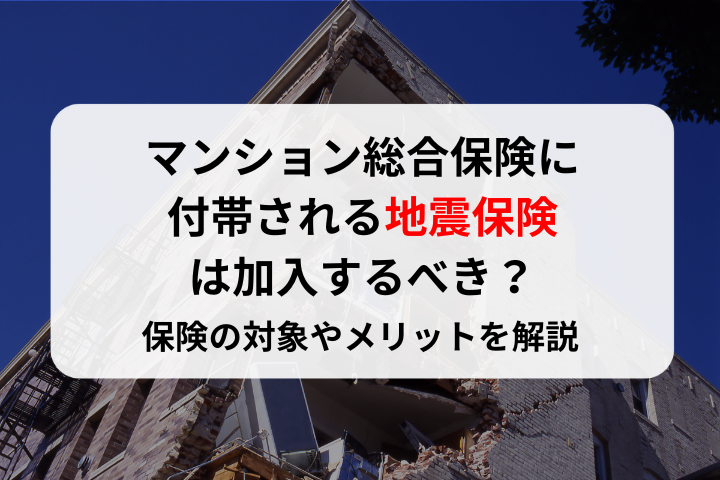
地震保険の加入について迷っていませんか?
「本当に必要なのか」「修繕積立金で十分ではないか」といった疑問は自然なものです。
多くの方が、マンション総合保険を見直す際にこの問題に直面します。
しかし、地震大国である日本では、地震保険の重要性を軽視できません。
そこで本記事では、マンション総合保険に付帯される地震保険のメリットや、加入時の注意点、保険料の決定要因などを詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、地震保険について理解を深めていただければ幸いです。
1.マンション総合保険に付帯される地震保険には加入するべき
 マンション総合保険に付帯される地震保険は、加入するべきと言えます。
マンション総合保険に付帯される地震保険は、加入するべきと言えます。
地震大国でもある日本には、地震のリスクが常に存在しているからです。
地震やそれに伴う津波、噴火による被害に備えることは、マンション管理において欠かせません。
地震保険は、マンションの専有部分や共用部分に対する地震、津波、噴火による損害をカバーします。
例えば、東日本大震災では、多くのマンションが深刻な被害を受け、その復旧には多額の費用がかかりました。
内閣府が調査した、住宅・生活の再建にかかる費用が、以下の表です。
|
項目 |
金額 |
|
全壊被害に遭った住宅の新築費用(平均) |
約2,500万円 |
|
公的支援として受給できる金額(義援金含む) |
約400万円 |
つまり、マンション総合保険に付帯される地震保険は、さまざまなリスクに対処できる大きな安心材料となります。
地震大国である日本の現状を考えると、管理組合の役員の皆さまには、地震保険への加入を強くおすすめします。
地震保険に加入しないと現実的に起こること
地震保険なしでは、地震発生後の生活再建が非常に困難になる可能性があります。
地震は予測が難しく、発生すれば甚大な被害を引き起こすからです。
特に分譲マンションのような集合住宅では、建物全体が被災した場合、住民全員で修繕費用を負担する必要が生じます。
そのため、各家庭への負担額が高額になる可能性が高く、無保険で修繕費を自己負担するのは難しいです。
例えば住民から以下のような意見が出ることも考えられます。
- 「10階にはほとんど被害が無いのに、1階と同じ割合で修繕費を負担するのは納得ができない。」
- 「修繕積立金で賄えない分の修繕費が高すぎて支払えない。」
- 「地震発生後1年も経過しているのに、修理がされないと資産価値が戻らない。」
このように、マンションでは様々な価値観の人が生活しているため、住民の意見が一致しないこともあります。
ですので、修繕費用に充てられる地震保険が必要になるのです。
2.地震保険の対象範囲

管理組合が加入する地震保険は、主にマンションの共用部分の損害を補償対象としています。
具体的に、地震によって損傷を受けた場合、補償の対象となる共用部分は以下のとおりです。
- エレベーター
- 廊下
- 外壁
- 屋上
- 階段
- 共用の給排水設備
- 電気設備
これらの共用部分は、マンションの機能を維持するうえで欠かせません。
地震による損傷の修復には多額の費用がかかりますが、地震保険に加入することで、この修復費用の一部を補償してもらえるため、管理組合の財政的な負担を軽減できます。
一方で、各住民の専有部分(室内の壁や床、個人の家財など)は、通常、管理組合が加入する地震保険の対象外となります。
これらについては、各住民が個別に地震保険に加入する必要があるものです。
3.地震保険に加入する3つのメリット

地震保険に加入することで、管理組合や住民には多くのメリットがあります。
ここでは、地震保険加入の主な3つのメリットについて詳しく解説します。
- 再建・修復費用の補助が受けられる
- 地震による火災への対応が受けられる
- 精神的な安心感が得られる
それでは、各メリットについて詳しく見ていきましょう。
メリット1.再建・修復費用の補助が受けられる
地震保険に加入すると、地震で建物や共用部分が損傷した際に、修理や再建費用の一部が補償されます。
これにより、住民や管理組合の経済的負担が軽減されます。
補償の対象となる例は、以下のとおりです。
- 外壁のひび割れ
- 基礎部分の損傷
- 室内設備の破損
- マンションの全壊
このような経済的支援により、被災後の復旧作業がスムーズに進み、住民の生活再建が容易になります。
つまり、地震保険は被災後の経済的負担を和らげ、復興を後押しする役割を果たすわけです。
メリット2.地震による火災への対応が受けられる
地震保険の重要な特徴として、地震に起因する火災に対応できることも挙げられます。
一般的な火災保険では、地震が原因の火災は補償対象外となることが多いのですが、地震保険ではこのようなケースもカバーできます。
例えば、「料理中に地震が発生し、火が建物全体に燃え広がった」というケースを考えてみましょう。
このような状況では、通常の火災保険からの補償を受けられないことが多いものです。
しかし、地震保険に加入していれば、このような地震が原因で起こった火災への対応ができます。
このように、地震の直接的な被害だけでなく、二次災害としての火災リスクにも備えられることで、マンション全体の安全性が高まります。
地震保険は、地震とそれに関連する火災リスクを包括的に保護する役割も担っているのです。
メリット3.精神的な安心感が得られる
地震保険加入の3つ目のメリットは、住民に大きな精神的安心感をもたらすことです。
地震は予測が難しく、被害も甚大になる災害です。
そのため、地震保険に加入していることで、万が一の事態にも対応できるという安心感を得られます。
特に地震が頻発する日本では、この精神的な安心感は非常に重要です。
つまり、地震保険は単なる金銭的な補償以上の価値があり、住民の心の支えとなる重要な役割を果たします。
この精神的な安心感こそが、地震保険加入の大きなメリットのひとつと言えるでしょう。
4.マンション総合保険の地震保険に加入する際に知っておくべきこと

マンション総合保険の地震保険に加入を検討する際、知っておくべき事項があります。
以下の内容を正しく理解することで、より適切な判断ができるでしょう。
- 地震保険単独で加入できない
- 補償範囲としてカバーされない範囲がある
- 補償額の上限がある
- 損害の程度によって支払われる保険金額が異なる
それぞれの点について、詳しく紹介します。
(1)地震保険単独で加入できない
マンション総合保険の地震保険は、必ずマンション総合保険の火災保険に付帯する形で加入する必要があります。
マンション総合保険に入っていなければ、地震保険だけを別途契約することはできません。
この仕組みは、地震リスクだけを選択的に保険でカバーすることを防ぐためのものです。
管理組合の役員として、マンション全体の保険契約を見直す際には、以下の順序で進めましょう。
- マンション総合保険の内容を確認する
- 地震保険の追加を検討する
地震保険はマンション総合保険とセットで考えなければなりません。
(2)補償範囲としてカバーされない範囲がある
マンション総合保険の地震保険は、地震や火山の噴火、津波による直接的な損害をカバーしますが、すべての損害に対応するわけではありません。
管理組合の役員として、以下の損害範囲を正確に理解しておくことが大切です。
- 地震後の火災
- 液状化現象による損害
- 貴金属や骨董品などの一部の家財
- 地震による間接的な損害(営業中断による損失、避難生活に伴う追加費用など)
マンション全体の安全を考える上で、カバーされない範囲を把握し、必要に応じて追加の対策を講じることが重要です。
例えば、共用部分に高価な美術品がある場合、その保護について別途検討が必要かもしれません。
ポイントは、地震保険の補償範囲を正確に理解し、マンション全体のリスク管理の一部として捉えることです。
カバーされない部分については、別の対策を講じるか、そのリスクを受け入れるかを、管理組合で議論しましょう。
(3)補償額の上限がある
マンション総合保険の地震保険の補償額には上限が設定されており、火災保険の保険金額の30%から50%までで決定した範囲内となっています。
例えば、建物の火災保険の保険金額が2,000万円の場合、地震保険の補償額は600万円から1,000万円までです。
つまり、実際の被害がこれを上回る場合でも、設定された上限以上の保険金は支払われません。
この上限は、大規模な地震発生時に保険会社の支払能力を超えないようにするための措置です。
しかし、マンション全体の再建や大規模修繕を考えると、この補償額では不十分な場合も考えられます。
そのため、管理組合としては、地震保険の補償額だけでなく、修繕積立金の状況や、他の資金調達の可能性も含めて検討しなければなりません。
(4)損害の程度によって支払われる保険金額が異なる
マンション総合保険の地震保険では、建物の損害の程度によって支払われる保険金額が異なります。
損害は4段階に分けられ、それぞれの程度に応じて保険金が支払われます。
|
損害の程度 |
支払われる保険金額 |
|
全損 |
保険金額の100% |
|
大半損 |
保険金額の60% |
|
小半損 |
保険金額の30% |
|
一部損 |
保険金額の5% |
つまり、被害が軽微な場合、受け取れる保険金は比較的少額になります。
この仕組みは、大規模な地震災害時に、限られた保険金を公平に分配するためのものです。
しかし、軽微な損害でも修繕費用が発生することを考えると、保険金だけでは不十分な場合もあるでしょう。
地震保険に加入する際は、この支払い基準を十分に理解し、軽微な損害に対しても対応できるよう、修繕積立金などの他の資金源も併せて検討することが重要です。
5.地震保険料の相場はどのように決まる?

地震保険料の相場は、さまざまな要因によって決定されます。
地震保険料を決定する主な要素には以下のようなものがあります。
- 建物の所在地
- 建物の構造
- 補償金額
- 契約期間
この要素がどのように保険料に影響するのか、詳しく見ていきましょう。
決め方1.建物の所在地
地震保険の保険料を決める際、建物の所在地が大きく関わります。
地域によって地震リスクが大きく異なるためです。
例えば、以下のような地域は地震リスクが高いとされています。
- 首都圏(東京、横浜など)
- 東海地域
- 活断層が多い地域
一方、地震リスクが比較的低い地域では、保険料も抑えられます。
このことから、管理組合の役員として、自分たちのマンションがどの地域に分類されるかを理解しておくことが大切です。
地震リスクの高い地域に立地している場合、保険料は高くなりますが、それだけ保険の必要性も高いと言えるでしょう。
つまり、建物の所在地は地震保険料を決める重要な基準であり、地震リスクの高低が直接的に保険料に反映されるのです。
決め方2.建物の構造
建物の構造も、地震保険料を決定する重要な基準です。
一般的に、建物の耐震性能が高いほど、地震による被害のリスクが低くなるため、保険料も抑えられる傾向にあります。
建物の構造別に見る地震に対する特徴や、保険料の傾向をまとめた表が以下のとおりです。
|
建物の構造 |
特徴 |
保険料の傾向 |
|
木造 |
地震の揺れに弱い |
高くなりやすい |
|
RC造・SRC造 |
地震に対する耐性が高い |
比較的低い |
|
新耐震基準(1981年以降) |
耐震性能が高い |
低くなることが多い |
管理組合の役員としては、自分たちのマンションの構造や建築年を確認し、それがどのように保険料に影響するかを理解しておくことが重要です。
耐震性能が高い建物であれば、それだけ保険料を抑えられることが多くなります。
決め方3.補償金額
地震保険の補償金額も、保険料を決定する重要な基準です。
地震保険の補償金額は、火災保険における保険金額の30%から50%の範囲で設定されます。
この範囲内で、より高い補償金額を選択すれば、それに応じて保険料も高くなります。
そのため、マンションの価値や想定される被害額を考慮しながら、適切な補償金額を選ぶことが重要です。
補償金額と保険料はトレードオフの関係にあり、マンションの状況や管理組合の財政状況を考慮しながら、最適なバランスを見つけましょう
決め方4.契約期間
契約期間も地震保険料に影響を与える基準のひとつです。
地震保険は通常、火災保険と同じ期間で契約されますが、契約期間の選択によって保険料に違いが出ます。
一般的に、地震保険の契約期間は1年~5年から選択可能です。
そして、長期の契約を選ぶと、保険料に割引が適用されます。
管理組合の役員としては、この長期契約のメリットを理解し、マンションの状況や管理組合の方針に合わせて適切な契約期間を選ぶことが重要です。
長期契約を選択すれば保険料を抑えられる可能性がありますが、契約内容の見直しの機会も減ることに注意が必要です。
契約期間の選択が保険料に影響を与えることを認識し、長期契約のメリットとデメリットを十分に検討したうえで決定してください。
6.マンション総合保険の地震保険について正しく理解しておきましょう
地震大国日本において、地震保険はマンションの資産価値を守り、住民の安全を確保するための重要な手段です。
ただし、その内容を正しく理解し、自分たちのマンションに最適な選択をすることが大切です。
迷った際は、専門家に相談するなどして、十分な情報を得たうえで判断することをおすすめします。
少しでも興味がありましたら、ぜひお声がけください。
マンションドクター
火災保険に関する
お問い合わせはこちら
マンションドクター火災保険ご相談窓口
0120-585-231
平日 9:00~17:00(土日祝休み)
Webでのお問い合わせ